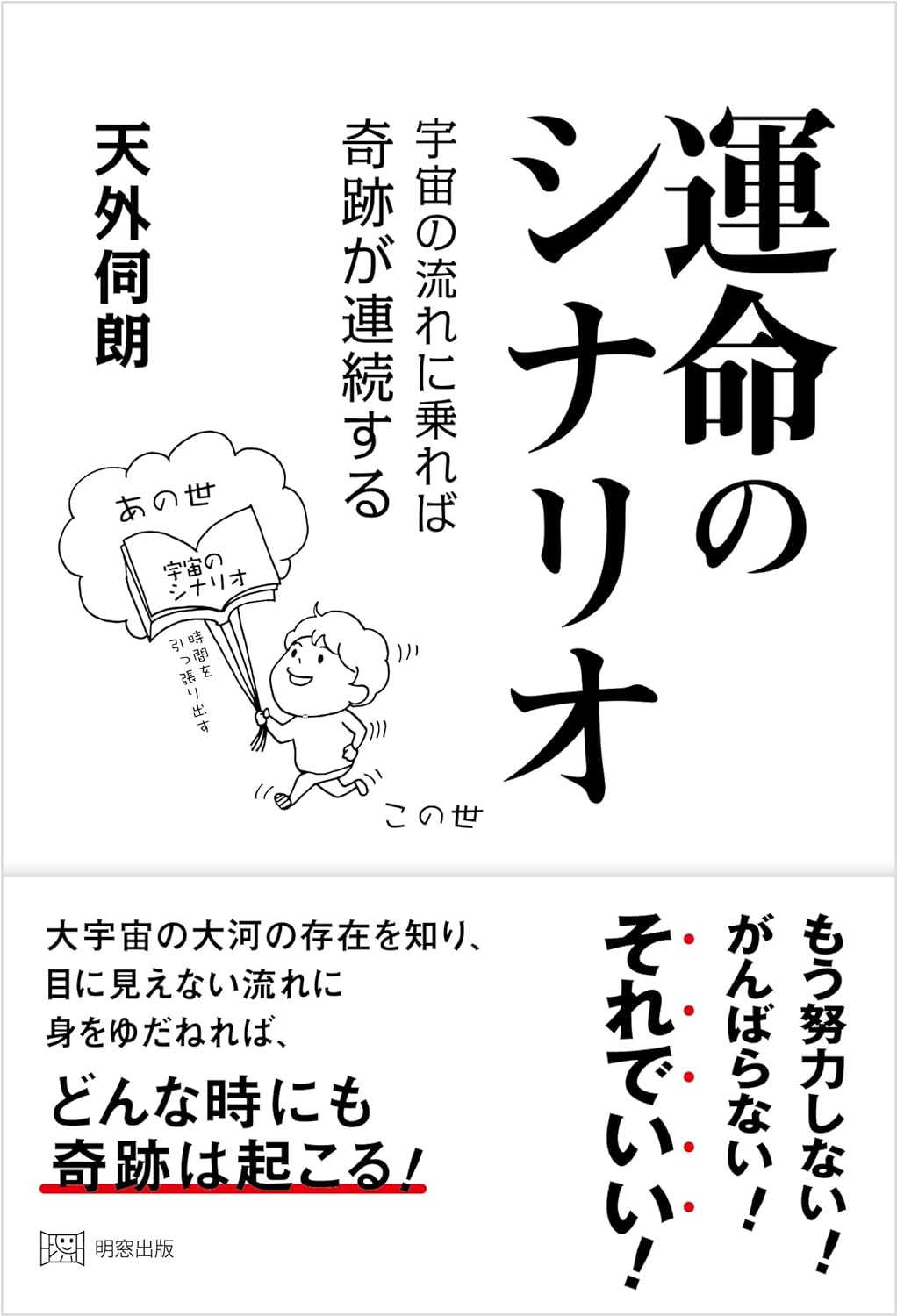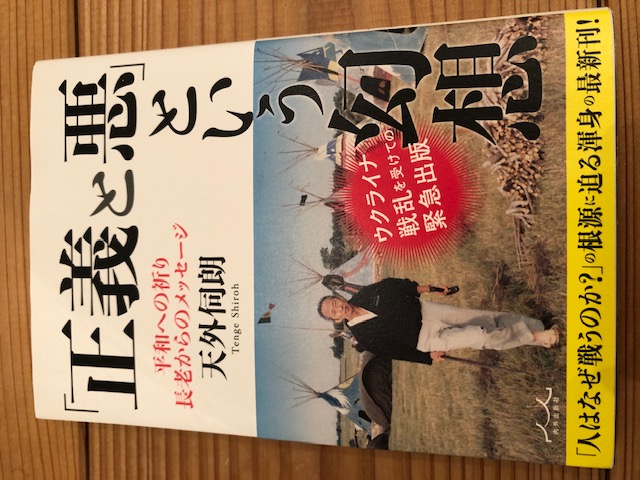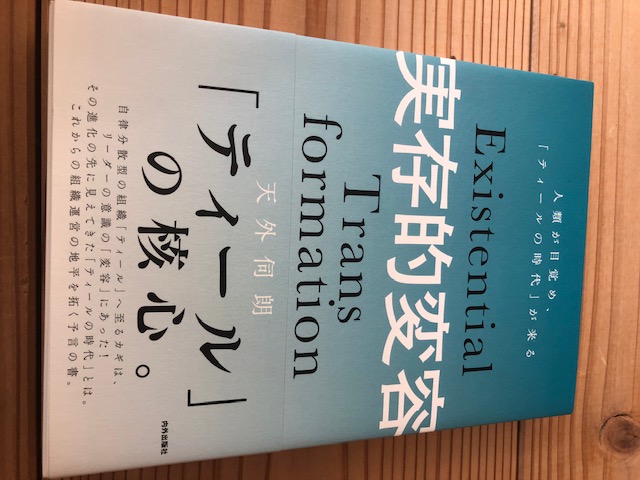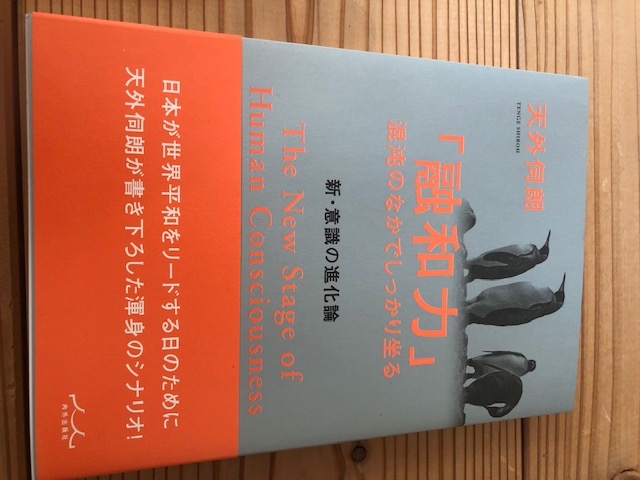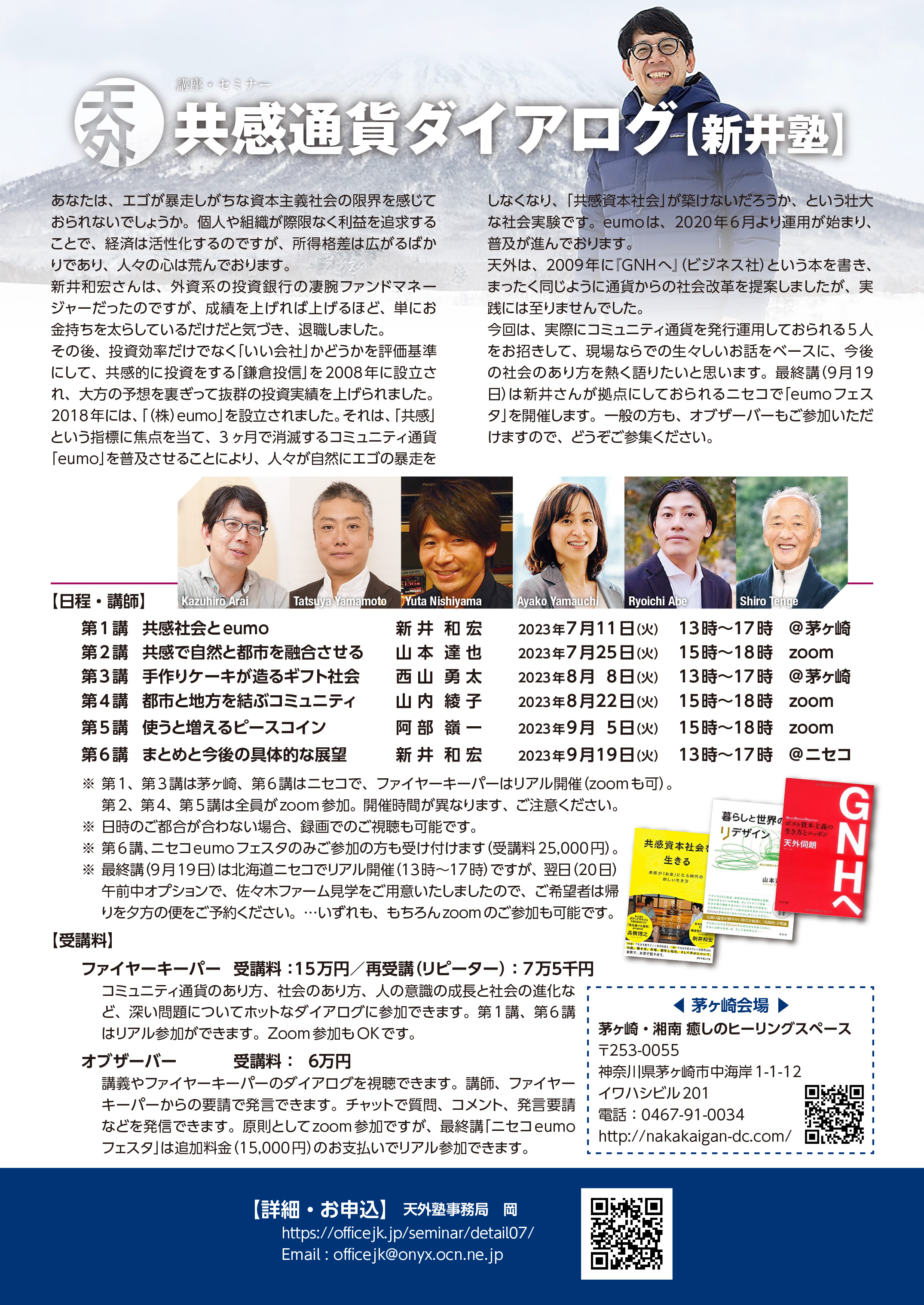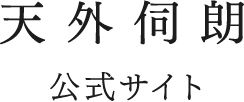- 天外伺朗公式サイト トップページ>
- 天外スクール
天外スクール
スタートから 一年間のサポート
天外が塾生に一年間寄り添うという「天外スクール」が、9月から始まります。
意識の変容のお手伝いは、中々短期間では完結しないので、じっくりお付き合いさせていただくためにこれをプランしました。
全6講の前期、後期の「天外塾」
「親子の葛藤」
「インナーチャイルド」
「インディアンの長老の叡智をお伝えするワーク」
「死と再生の瞑想ワーク」など全3講の瞑想ワーク
全4講の「宇宙の流れに乗る生き方塾」などのセミナーが自由にご受講いただけます。
「天外塾」は、毎回内容が違いますので、二回の受講は意義があります。
上記セミナー以外は含まれませんのでご注意ください。
概要は以下の通りです。
1.定員10名
2.期間は一年間限定です。
3.「天外スクール」初受講料:¥850,000-
4.「天外スクール」の再受講料(翌年受講の場合)¥600,000-
5.下記のセミナーが対象です。
(これ以外のセミナーは対象外なのでご注意ください)
①「宇宙の流れに乗る生き方塾」09/20,10/04,11/01,12/06
受講料(単発) ¥200,000(再受講料(単発)¥100,000)
②「天外塾2025年度後期」10/11,11/15,12/13,2026/01/17,02/07,03/07
受講料(単発) ¥300,000(再受講料(単発)¥150,000)
③「インディアンの長老の叡智をお伝えするワーク」10/25,11/29,12/20
受講料(単発) ¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)
④「死と再生の瞑想ワーク」2026年01/24,02/14,03/14
受講料(単発)¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)
⑤「天外塾2026年前期」2026年04/06,05/09,06/06,07/04,08/01,09/05
受講料(単発) ¥300,000(再受講料(単発)¥150,000)
⑥「親子の葛藤を解消するワーク」2026/04/11,05/23,06/20
受講料(単発) ¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)
⑦「インナーチャイルドワーク」2026/07/18,08/15,9/26
受講料 ¥150,000(再受講料(単発)¥75,000)
*9月以前のセミナーに関しては対象外です。
*この7つのセミナーがワンサイクルで、
順番に繰り上がります。
*合計受講料 ¥1,250,000が割引きで、¥850,000
*全部再受講だと¥700,000が割引きで、¥600,000になります。
現在、2025年9月期のお申込を受付中(2024年9月生は満席)。
定員になり次第、予告無く締切りますので、
ご希望の方はどうぞお早めにお申込ください。